|
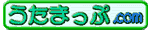 |
|
まばたきのあいだに、
|
| 作詞 憂鬱な画家と陽気な庭師 |
|
「こんな世界はなくなればいいと少女は言った。何処からともなく聞こえてくる警笛の音が、悲劇の輪郭を鮮明にしようとする。テレビの中でデモ隊が鎮圧されていた。正義をこじらせて銃を使うのは馬鹿らしく思う。とある詩人らはこの世界を奇跡だと言う。誰かの犠牲を振りかざして、それを讃えるたくさんの寸劇に。鳴り止まない拍手。揺れる赤い欺瞞。何年も前から鼓膜には、『生きたい』という台詞がこびりついている。それでも詩人らがこの世界を奇跡だと歌うのならば、僕には死ぬのも生きるのも、まったく同じような奇跡に見える」
「また一人、ここから飛び降りていった。止まっている時計の針のせいで時間は剥製になっている。恐怖心はだんだんと薄れていき、これ以上ないくらい穏やかな気分だった。笑い転げる太陽は、剥き出しの心に突き刺さる。もうすぐ彼は世界から吐き出されてしまうのだろう。目を瞑ってゆっくりと重心を前にもっていく。風はとても静かに、でも勢いよく体を包み込んだ。感じたことのない感覚のなか、彼は目を開ける。やはり時間は剥製にされていた。全てが止まっている。彼だけが動いている。それはそれで神秘のようにも思える。手を広げて体を空へとひるがえす。きっと何もかもが終わった後、時間はやっと元に戻る。絵画のような空がその光景を見下げていた」
「まばたきのあいだに、たくさんの核心が生まれる。他人事のようなニュースがただの認識になった時、とんでもなく冷酷な人間になったように思う。何かを失うことを有り触れたものとしか感じられない。リアルとフィクションの境目がよく分からない。質の悪いロールプレイングゲームの住人のように、僕は同じことを繰り返す。昨日までの楽しかったこと、悲しかったこと、急に全てが嘘かのような錯覚に襲われる。名前も知らないあの子のシナリオから見える僕は、どんな人間なのだろうか。いや、きっと取るに足りないものだ。僕がいなくなったところで、それは欠落ではない。もともとそんなものは存在していない」
「僕は生きるよ。ただ生きるよ。君も生きてよ。ただ生きてよ」
「あの日、産道を通って最初に見た光景は、ただの白い光だ。目も開けていられないような圧倒的な光だ。柔らかな母の体温だけを感じていた小さな身体は、その瞬間がくると産声を上げる。初めて見た光は、きっと恐ろしいものでしかなかった。知らないのに、知っている。分からないのに、分かってしまう。ただの生命体でしかなかった頃に埋め込まれた記憶は、形などなくても鮮明に焼き付いている。言葉ではない何かは時に、何もかもを超越した理解だけをくれる。きっと、これから僕の身に起こる出来事も似たようなもので、言葉では表現できない領域がほとんどをしめるだろう。ありとあらゆるそれらを言葉で伝えようとしては、諦めてしまうだろう。強い光ほど、その出所は分からないまま。でも僕は目を凝らす。その光の向こうを見ようとして」
|
|
|

