|
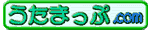 |
|
きみ
|
| 作詞 謡 |
|
見送ったバスが小さくなって
街が夕暮れに染まる
二人歩いてきた道を
一人歩く僕がいる
街路樹を揺らした風が
夏の終わりを告げているようだった
人影のないこの小さな公園で僕らは出逢った
きみが好きだと言った線香花火が照らしたその横顔を
忘れることはないでしょう
小さな火を大切に見つめる瞳の奥に見つけた気持ちを
守っていきたいと思ったんだ
夏を過ごしたこの部屋で
風を刻んだこの風鈴
音が鳴るたびにきみを思い出して
それでもしまうこと出来ない僕は
やっぱりきみを
忘れることはないでしょう
初めて二人で行ったあの海と夏の陽に
よく似合っていた水玉のスカートは
今は誰の隣で笑っているのだろう
波の音に溶け込むように消えた
きみの声を
忘れることはないでしょう
楽しいはずだったあの日
些細なひとことが生んだすれ違いを
天気のせいにして
きみと距離をおいた
夕立ちの雨音が不安にさせた
きみの頬を伝った初めて見たその涙を
忘れることはないでしょう
やがて過ぎていく季節を察したきみのかおに
気づかないふりをして思いきり抱きしめた
いつかこの腕の中から去りゆくきみのあたたかな感覚を
忘れることはないでしょう
きみと過ごしたいくつもの日々が
二人の心にあるのなら
また巡りあえる時が来るでしょう
その時まできみを忘れることはないでしょう
きみを忘れることはないでしょう
|
|
|

