|
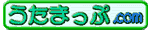 |
|
散文詩
|
| 作詞 ポリンキー |
|
「納豆じゃだめなのよ」
蒸し暑い日だった。出掛けに見た天気予報では、今日は40度まで達するという。熱射病、日射病に注意といっていた。僕は、だれて机に突っ伏していた。家庭部の登校日には、僕とアイの2人しかいなかった。あまりに厚いからみんなや担って部活なんかサボるんだろう。それが普通なんだ。夏休みじゃなくたって、この部活は僕とアイしか、普段は来ないんだから。僕はスタイリストになりたくて、毎日ミシンを踏んでいたから、よく来ていた。アイは料理の鉄人になりたいらしく新メニューの開発に余念がなかった。しかし、今日はあまりに暑すぎるため、さすがの僕たちもやる気がなかった。家庭科室の机に突っ伏して、僕はぼやいた。
「冷たいそばが食べたい」
「それよ!
叫ぶとアイは立ち上がって猛然と動き始めた。鍋を火にかけ、具材を切ってざるに入れていく。実に手際がいい。沸騰した鍋に、アイはそばをばらばらと裁きいれた。
「すぐできるわ」
アイの料理の腕は知っているので、僕は口の中がつばでいっぱいになった。
はやくできないかな。待ち遠しい思いで待つ。その間にもてきぱきと動くアイはいつもよりもきれいに見えた。暑さのせいか思わず、
「キレイだ」
とつぶやいた。
アイは、びっくりした顔でこっちを見た。よそ見したので、指を切った。
「大丈夫?」
立ち上がって近づく、
「うん、あちょ、こないで」
指を切っていない右手で僕を押しとどめる。目が警戒している。
「わかった、君のテリトリーには入らない」
両手を挙げていうと、僕はいすに戻った。
それからのアイはらしくなかった。いつもの機械のように正確な包丁さばきも、スムーズな順序だてた動きも精彩を欠いていた。
「アイ本当に・・・」
「平気なんだから!」
激しい口調に僕は黙り込んでしまう。
アイはいよいよ無口になった。
僕は、どうしていいかわからずに、机に突っ伏した。
「桐谷アイって、かわいいよな」
そういっていた同じクラスの男子連中の会話を思い出していた。僕はあいまいにうなづき、頭の中では、そうでもないと思っていた。近すぎて、兄弟みたいなものだった。意識する対象ではなかった。どちらかというと、陸上部の小早川さんに、僕はご執心だった。
そばが茹で上がったらしい。アイがざるにあげる。
|
|
|

