|
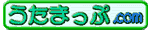 |
|
六つの恋愛アンソロジー
|
| 作詞 雫依瑠子 |
|
とるに足らない小さな夜はいつの間にか飲めもしないお酒の中へ沈んで、
指環もできない決定的な痛みと、体内へ流し込めない幸福感を想った。
沈黙こそ極上の音楽、と紅い具現化の真偽判定を押しやって、
目覚めと同時にそれを口紅で一なぞり、願わくば、心にまで沁み付いて消えない跡。
胸中の水桶にふいに舞い落ちた言の葉は、安心と呼ぶには程遠く不確かで、
ただ確実に一握りの腐葉土となって、心を生かしていく。
徐々に溶けてはほぐれて優しい毒となって、それは哀しい程無様で、
こっくりとした甘さをもって、リアルな栄養素となっていく。
例えばそれは如何し様もないジョーカーで、絶頂ともどん底ともつかない口元で全てを惑わせる。
甘い香りの香水だって、舌に乗せれば痺れる様に苦いし、
優しさの象徴の様な石鹸でさえ、その味を試すわけにはいかない。
唯一、其処に残るのは、癖になる陶酔。
空気が色づく瞬間の存在も、其処に散りばめられた無数の幸福と刹那と疼痛の粒子も、
それらが心に導く、制御不可能の化学反応も。
何もかもが、「想定」という概念を根本から覆していく。
研ぎ澄まされていく五種類の感覚と、生活が意味付けられていくという確固たる事実。
片手で握り締めた四角い世界で、歌と光が知らせるメッセージに心の灯をともして、
その向こう側に在る伏線を探ろうとする。
いつも唐突過ぎるが故に降り積もる、無駄の代名詞とも呼べる開閉作業。
それでも、体の中にはずっとずっと、音が鳴り響き続けていく。
好みが増え、習慣が増え、広がりきった世界の終焉は、いつも悲しく明るい。
すぐに次の日差しを求める程の強さは生憎皆無で、
今はそれを信じる事も出来ず、只願う。
小説の中の主人公は、いつだって歳をとらない。
それは、恋だった。
|
|
|

